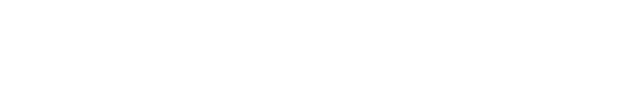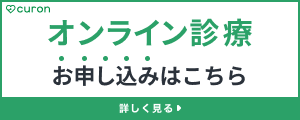ながくらクリニック通信vol38 (2011/2/10)
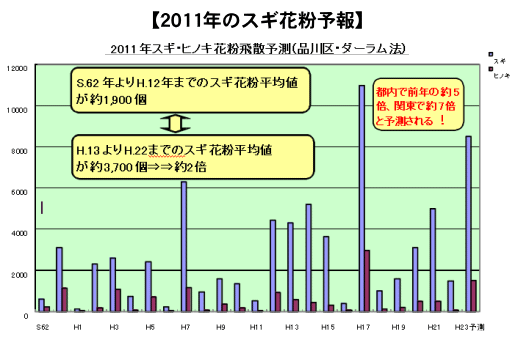
| 2011年スギ花粉飛散予報 | |||||||||||||||||||||||
|
1.スギ花粉総飛散量(ダーラム法) 2.飛散開始 ◎総飛散量が非常に多いことの影響を受けて、 ◎総飛散量が非常に多いことの影響を受けて、 ◎症状の重症化を起こしやすい50個/cm2以上の日が、シーズン中、40日はあると予想され、花粉症対策を、早期より十分に実施する必要であることが、発表されました。 ◎今年は、2005年の測定史上最高の飛散に次ぐ、第2番目の大量飛散になる予想と発表されました。 ①2010年度は、7月の最高気温は高かったが、日射量が2005年より少なかった。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
① 治療法 Ⅰ Q1予防的治療(初期療法)はいつから始めるのでしょうか? 治療開始は、症状の発症を軽くするため飛散開始より2週間前より(予防的治療)、あるいは、軽症のうちに開始し、シーズンを通じて鼻粘膜の過敏性を高めないことが大切です。 Q2.治療にはどのような薬をつかうのでしょうか? 使用する治療薬は、大きく分けて以下のようです(鼻アレルギー診療ガイドライン 2009年版による)。 Q3.内服薬を飲むと眠気があり、薬を飲めないのですが? 近年使用される治療薬は、眠気の少ない第2世代の抗ヒスタミン作用を持つ抗アレルギー薬が多くでてきています。しかし、仕事能率を低下させないもの、車の運転などに影響のないものなど、使用状況にあった薬剤の選択が望ましいといえます。また内服薬でどうしても眠い場合には、点鼻薬を使用する、抗ロイコトリエン薬などを併用する方法があります。 Q4.抗アレルギー薬の副作用でインペアード・パフォーマンスというのはどうゆうものですか? 「気がつかれない作業能率の低下」とも解釈され、クシャミ・鼻水・鼻閉などをおさえる抗ヒスタミン薬には眠気を起こす作用があります。最近開発された薬は、作業能率、注意力、脳波に影響をよりおよぼさないものが開発、使用されるようになっています。 Q5.副作用が心配なのですが? ①内服で使用する抗アレルギー薬・抗ロイコトリエン薬などについては、アレルギー疾患の治療・コントロールのため長い場合には数年使用する場合にも安全性が確認されています。しかし、薬の薬理作用を考慮すると100%安全というわけではありません。 【スギ花粉情報参考WEB】 ②治療法 Ⅱ Q6.妊娠中・授乳中は薬を使えるのでしょうか? また妊娠が分かった時はどうでしょうか? 基本的に治療薬の使用は避けた方が良いと判断されています。 Q7.市販薬と処方薬の違いは? 市販薬(OTC)は、「誰にでも、おおよそ効果が期待できるための物」です、それに対し、診察して処方する薬は、個人の症状・病態・他の治療との相互作用を判断し、そのときの症状に最も適切な処方をします。また処方薬に含まれる有効成分は、一般に市販薬より多く、そのため、より効果的であり、また医療保険の適用もあり経済的でもあると言えます。 Q8.ジェネリック(後発医薬品)とはどうゆう薬ですか? 処方される薬には、最初に製品を開発、臨床試験に合格して治療薬して認められた新薬(先発医薬品)と、発売後年数がたち特許がきれると、ほぼ同じ成分としてジェネリック医薬品(後発医薬品)が許可される場合があります。後発医薬品は、医薬品の開発費が必要でないためコスは安くなりますが全く同じ薬という訳でもありません。有効成分以外の成分が異なる場合、剤形が異なることなどがあり、安全性・薬効も先発品と全く同じ物でもありません。(当クリニックでは、ジェネリックとして信頼できる物を選び使用することがあります。しかし、すべての後発医薬品を把握することは困難なため、希望の場合は診察の際お尋ね下さい。) Q9.注射で治療をすると聞きましたがどのような治療でしょうか? 花粉症をステロイド注射で治療をする場合があります。ケナコルトというステロイド薬を筋肉注射(上腕または、大量の場合は、臀部(おしり))することが多いようです。副腎皮質ホルモンを大量に注射するわけですから、女性では、ホルモンバランスが崩れ、生理が変わるなどの症状、また、高血圧・糖尿病・循環器疾患・緑内障・白内障などの基礎疾患を合併する場合は、特に副作用の発現に十分注意しなければいけません。(鼻アレルギー診療ガイドライン2009でも、花粉症の治療法には入っていません。)また、ステロイドは脂肪組織の萎縮を起こし注射部位の陥没を起こしたことも報告されています。 現在、アレルギーの治療薬は進歩していますので、これらの治療法で十分症状を軽減できると考えています。 Q10.減感作療法とはどのような治療法でしょうか? 自分の体に対しアレルギーの原因である物質(花粉症の場合、「スギ治療用エキス」)を現行では、少量より注射量を増量してゆくことにより、過敏性を抑制して、アレルギー反応を起こさないよう免疫システムを変えてゆく治療法です。 ③症状について Q11.スギ・ヒノキの花粉はいつ始まり・いつ終了するのでしょうか? ◎スギ花粉の飛散開始は、例年2月上旬から中旬に始まり4月にはいると終了します。 Q12.鼻づまりがつらいのですが、良い治療薬がありますか? 花粉によるアレルギー反応により、肥満細胞(マスト細胞)より放出・産生されるヒスタミン・ロイコトリエンのどの物質が、クシャミ・鼻水・鼻閉などの鼻症状を引き起こします。特に鼻閉に対し、抗ロイコトリエン薬の使用が効果的であることが確認されてきました(参考:鼻アレルギー診療ガイドライン2009)。 Q13.咽頭の痛み・耳症状・熱感・発熱などがありますが、風邪との違いは? 花粉症は鼻のみの症状でなく、耳・咽頭・喉頭の症状、全身のだるさ、軽度の発熱の症状を合併します。そのため、発症の初期には風邪と区別がつきにくいことがあります。具体的診断には、皮膚検査・血液検査により診断をしますので専門医にご相談して下さい。 Q14.2才の子供が今春鼻水・鼻閉・眼のかゆみ等を訴えるのですが?(子供の花粉症) 花粉症発症の低年齢化が進んでいます。早い場合1歳(2シーズン目に発症する子供を診察する事もあります。)で発症することもありますので受診してご相談して下さい。 Q15.両親が花粉症なのですが、生まれた子供が花粉症に発症することを予防できるのでしょうか? 花粉症に発症するか・しないかは、個人の遺伝子、発育時の環境などが影響して決定すると考えられます。しかし、発症のリスクを軽減させる方法としては、スギ花粉症に時期に花粉との接触をなるべく少なくする、生後からの離乳食の取り方、生活環境・衛生環境において、注意できる点を改善することなどが、有効であると考えられています。 Q16.花粉症の時期になると咳発作がとまらないのですが?-咳喘息についてー 花粉症の時期に、鼻アレルギーや喘息などのアレルギー疾患のある場合、下気道の過敏性が高まり咳発作を起こしやすくなることがあります。咳喘息とも呼ばれ、気管支の炎症・過敏性を改善するため、抗アレルギー薬、抗ロイコトリエン薬、吸入ステロイド薬などで治療します。 Q17.花粉症は高齢になれば症状がなくなりますか?また高齢で発症もありますか? 加齢による免疫機能の変化により、症状が軽症に(鼻水のみになるなど)なったり、症状の消失する場合も(60歳をすぎると約10%くらいとも言われています。)ありますが、その反面、60歳を越えてからの花粉症発症もあるため、(発症の高年齢化)現在、症状のつらい方は、まず現在の症状に対する治療が必要と言えます。 Q18.日本人以外の国籍の方も日本に来て花粉症になりますか? スギ、ヒノキの木は、世界的に見てほぼ日本に特有に分布しています。日本においては、厳密には、北海道と沖縄にはほぼ生育しません、また中国大陸(中国杉)、北米(ロッキーマウンテン・シダー)、南米など地球の温帯地域に存在します。また、これらの木の花粉の抗原性はほぼ同様と分析させていますが、生息する地域はごくわずかです。 ④ 生活の注意点 Ⅰ Q19.花粉症で日常の注意することは(花粉症対策)? ①花粉に鼻・眼に入らないよう予防対策を立てる。 Q20.花粉グッズの選び方は? ①マスクの選び方 (追加項目:手術) Q21.手術療法について 治療薬によっても鼻閉・鼻汁過多などが十分改善されない場合、手術の適応となり、①鼻中隔湾曲矯正術 ②下鼻甲介切除術などが行われますが、外来での日帰り手術として、レーザー治療・シェーバー・電気焼却など新しい手術器具が開発されてきました。 ⑤生活の注意点他 Ⅱ Q22.眼の症状に対する治療について 花粉症の時期には、抗アレルギー薬の点眼薬(インタール・ザジテン・リボスチン・パタノール点眼液など)や、抗アレルギー薬の内服を使用します。また、鼻症状に対し、花粉飛散前より予防的投与を行うことが効果的であるのと同様に、点眼を予防的に早期から行うことも有効です。 Q23.コンタクトレンズ使用の場合の注意点について。 点眼薬の使用法 Q24.スキンケアについてー花粉症皮膚炎― 花粉症の時期になると、皮膚のかゆみ、特に花粉が直接当たる顔の皮膚がかゆいなどの症状を訴える人がいます。花粉症皮膚炎とも呼ばれ、アトピー性皮膚炎・ドライスキンなどでバリアー機能の低下している状況でより起こりやすいと言われています。対策としては、マスク・帽子・めがね(ゴーグル)をして、花粉が直接皮膚に当たるのを避ける、ドライスキン・アトピー性皮膚炎の対策としてのスキンケアを十分して、皮膚のバリアー機能を低下しないよう注意すること、抗アレルギー薬を内服するなどの対処が大切です。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|